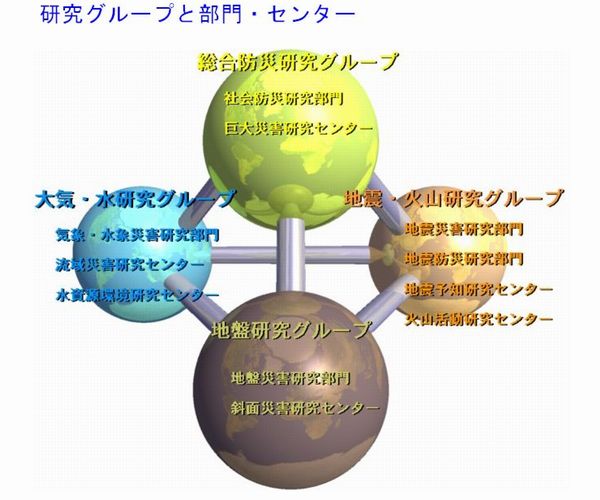����ޓ��e��
1. �S��
�P�j �ΖʍЊQ�����Z���^�[�S�̂Ƃ��Ă̖ړI�͉��ł����H
|
�n���ׂ�ɂ��ΖʍЊQ����l���E���Y�╶���E���R��Y���܂��邽�߂ɁA�n�k�E���J���̒n���ׂ蔭���^���@�\�̉𖾁A�n���K�͂ł̎ΖʍЊQ�̊Ď��V�X�e���̊J���A�n���ׂ�̃t�B�[���h�ɂ����錻�n�����E�v���Z�p�̊J���y�юΖʍЊQ�y���̂��߂̋���E�\�͊J�������{����B�܂��A�ΖʍЊQ�Ɋւ��鐢�E�I�l�b�g���[�N�̒��j�I�����Z���^�[�Ƃ��āA�ΖʍЊQ�y���Ɋւ��鍑�ۋ��������̊�撲�������{����B |
�Q�j �ΖʍЊQ�����Z���^�[�̖h�Ќ����ł̈ʒu�t���i�������O���[�v�Ƃ̂������j�́H
|
�|����h�Ќ������g�o���| |
�R�j ��Ȋ����ꏊ�i���������H�t�B�[���h�H�j�͂ǂ��ł����H
|
�������n���ׂ�ϑ����@�i�����n���ׂ�A�P���n���ׂ�A���R�̒n���ׂ蓙�j �������R��i���R�j�@�s�����ՎΖʊĎ��V�X�e�� �����@�����s�ؐ��r�i�k�M�܋{�a�j�@���R��鋎R�Ζʂ̒n���ׂ� �y���[�@�}�`���s�`����� |
�S�j ���ʂ̔��\�͂ǂ̂悤�ȋ@��ɂ����Ȃ��Ă��܂����H
|
�_�@�@���F���ۃW���[�i���uLandslides�v�CEngineering Geology, American Society of Civil Engineers�iASCE�j�Ȃǁc�_�����X�g�Q�� �������\�F���{�n���ׂ�w������\��CICL�V���|�W�E���CIPL�V���|�W�E���Ȃ� |
2. �ʌ����ۑ�ɂ���
�i�P�j��r�����I�ډגn���ׂ�Č������@�Ɋւ��錤��
�P�j�����g��ł��錤���T�v
|
(a)��K�͍Ċ����^�n���ׂ�̊댯�x�]���Ɣ�Q�y������ �@2004�N�䕗10���ɂ�蓿�������Í]�n��ő�K�͂ȎΖʕ����������B����ɂ��C�Â���K�͐[�w�n���ׂ肪�Ċ������C���݂��̓����������ɂȂ��Ă���B�{�����́C (1)�n���ׂ�̈ړ��ψʂ��v�����C����n���ׂ�̕���O�����ۂ�c������B (2)���ׂ�ʕt�߂���̎悵�������̂ɑ��āC�����O����f�������s���C����������f�ψʎ��̂���f���x�̕ω����𖾂���B (3)���n�ϑ��Ǝ��������̌��ʂ����K�͐[�w�n���ׂ�̕ϓ����J�j�Y�����𖾂���ƂƂ��ɒn���ׂ�̉^���͈͓���\������B (c)���^�n���ׂ�Č������@�Ɩ͌^�Ζʓy�w��p�����������\���̌`���ƍ����n���ׂ�̉^���@�\�̉� �@���^�̒n�k���n���ׂ莎���@��p���āC�y�w�������̉ߒ��ƃ��J�j�Y���𑽖ʓI�E���ؓI�ɉ𖾂��邽�߂̌��Ƃ��āC�����@���Œn���ׂ�E�Ζʕ���ɂ����邷�ׂ�ʂ��邢�͂���f�]�|���̌`�����Č������C�ő�����t���ɕω�����ߒ���͊w�I�v�f�i����f���́C�ߏ�Ԍ������C����f�ψʁ^���x�C�̐ϕω��j�̌v���C�y�ї�����Ԃ̊ώ@�ƃr�f�I�B�e�ɂ�鑬�x���z���v�����C����f�]�|���̌`���E���B�C���q�̔z��E�j�Ӊߒ����ώ@���āC�������\���̌`���y�э����n���ׂ�̉^���@�\���𖾂���B |
�Q�j�����_�̌������ʂ̒��œ��ɓ����I�Ȃ��Ƃ�
|
(a)�n�k�~�J���������������n���ׂ�͕����̉^���ɔ����y���̉t�����͂��ׂ�ʉt�ɂ�������̂������B�����C�t���ۂ������^���̌����ł��邪�C����̌��ʂł����邱�ƁB (b)���y�ɂ����ĉt���ۂƂȂ鐅���̔����E���U�́C�Ζʂ̌X�C�n���ׂ�y��̏������x�C�y������C���ׂ�ʕt�ߓy��̔j�Ӑ��y�ї��x���z�C�n�����ʂ̏�ԂȂǂɉe������邱�� (c)����f�]�|���ɂ��`�����ꂽ����f�]�|���̌����͂���f���x�ɊW�Ȃ�������f�]�|���ɂ����ēy���q�̕��z�͂���f���x�̕ω��ɔ����ĈقȂ邱�ƁB
|
�R�j����̌����̕�������
|
�E�Ċ����^�n���ׂ�̊댯�x�]���Ɣ�Q�y��������m������邱�� �E ����f�]�|���̌`���ƒn���ׂ�̍����^���Ƃ̊W���𖾂��� �E �~�J�ɂ��n���ׂ�̔��B�ߒ��y�є������Ԃ������x�ŗ\�����邱�� �E ��K�͒n���ׂ�ɑ��钷���ϑ��̂��߂̊ϑ��@��̊J�� |
�i�Q�j���R��Y�n��̒n���ׂ�댯�x�]���ƊǗ��Ɋւ��錤��
�P�j�����g��ł��錤���T�v
|
(a)�y���[�@�}�`���s�`����Ղ̒n���ׂ� (b)�����@�����s�ؐ��r�i�k�M�܋{�a�j���R��鋎R�Ζʂ̒n���ׂ� |
�Q�j�����_�̌������ʂ̒��œ��ɓ����I�Ȃ��Ƃ�
|
(a)���݁C�n�\�ʕψʂ̊ϑ������{���Ă���Ƃ���ł���B �ڍׂ́C���ےn���ׂ�w�p���uLandslides�v��C101-1�Q�� (b)�d�q�����X�p���L�k�v�ɂĕϓ��ϑ����ł���B |
�R�j����̌����̕�������
|
�E�y�Η��x�����ɑ���g�D�̍\�z �E100�`1000�N�ȏ�̃I�[�_�[�̎Ζʕϓ��̒����\�� �E���[�_�[���g��p�����Ζʌv���V�X�e���̓K�p �E�r�㍑�ɂ�����n���ׂ�댯�x�y���̂��߂̋���C�l�ފJ�� |
�i�R�j�j�ӑт̌����Њ�n���ׂ�̈ړ��ϑ��Ɋւ��錤��
�P�j�����g��ł��錤���T�v
|
(a)�������@�P���n���ׂ�C�����n���ׂ葼�C�����Њ�n���ׂ�̒����ړ��v������ђn�����ϑ����p���I�Ɏ��{���� (b)2004�N�䕗10���ɂ��U�����ꂽ���������Í]�n���K�͐[�w�n���ׂ�̕ϓ��Ɋւ���v������ �@(1)�n���ׂ�̈ړ��ψʂ��v�����C����n���ׂ�̕���O�����ۂ�c������B �@(2)���ׂ�ʕt�߂���̎悵�������̂ɑ��āC�����O����f�������s���C����������f�ψʎ��̂���f���x�̕ω����𖾂��� �@(3)���n�ϑ��Ǝ��������̌��ʂ����K�͐[�w�n���ׂ�̕ϓ����J�j�Y�����𖾂���ƂƂ��ɒn���ׂ�̉^���͈͓���\������B |
�Q�j�����_�̌������ʂ̒��œ��ɓ����I�Ȃ��Ƃ�
|
(a)�e��w��Ŕ��\���Ă���̂ŁC�����B�i�ʎ��_�����X�g�Y�t�j (b)���Í]�n���ׂ�́C�Ċ����^�n���ׂ�ł���C�䕗10���ȍ~�ϓ��������Ă���B�ړ��y��͓��������ǂ��C�~�J�Ƃ̑��ւ������ł���C�~�J���ɕϓ����������邱�Ƃ���C�~�J�ʂɂ��C�ϓ��\�������҂ł���B |
�R�j����̌����̕�������
|
(a)�펞�ϓ����Ă���n���ׂ��ΏۂƂ��邱�ƂŁC��w�@���C�Љ�l����ъC�O����̌��C�����ɑ��Ēn���ׂ�Ɋւ��鋳��E�l�ވ琬�̃v���O�����Ƃ��Ď��{���Ă䂭�B (b)�n���ׂ�̔����@�\���𖾂��邱�ƁB�n���ׂ�y��̑S�̖̂��x�ω��ƈړ������̊W���𖾂��邱�ƁB�n�k���̎R�n�ЊQ���y��������@���Ă��邱�ƁB |
3. ���Ԋ�ƂƂ̋��������ɂ���
�P�j����\�肵�Ă���e�[�}
|
�E���l�X�R�^���s��w�^ICL�i���ێΖʍЊQ�����@�\�j�ɂ��UNITWIN�v��̈�Ƃ��āCICL�ւ̖��Ԋ�Ƃ̎Q��𐄐i���邱�Ƃ���CIPL�i���ێΖʍЊQ�����v��j�Ɉʒu�t�����邠����Z�p�J���E���� �E �����O����f�^�n���ׂ�Č������@�����p�������� �E ���[�_�[���g��p�����Ζʌv���V�X�e���̓K�p |
2�j���̑��ɁA���݂ǂ̂悤�ȋZ�p���i�j�[�Y�j������܂����H
|
(1)�Z�p�J�� �E�Ď��Ƒ����x�� �E�n�U�[�h�}�b�v�쐬�A�Ǝ㐫����ъ댯�x�]�� (2)�d�_�n���ׂ�F���J�j�Y���ƃC���p�N�g �E����ЊQ�������N�����n���ׂ�i�~�J�E�n�k�E�ΎR�����E�͐�Z�H�E�l�I�����A�����̑g�ݍ��킹�ɂ��B�Ôg���j �E��Y���������n���ׂ�(��:�}�`���s�`���A�o�[�~�����ACordilleraBlanca) (3)�\�͊J�� �E�l�ԁE�g�D�\�͂̋����i���Ƃ̗{���A�����@�ւ̊J���A�n��ł̎������j �E���E�m���̎��W�E���M�i�ΖʍЊQ�댯�x�̔F�m�����̔��W�j (4)�y���A�\�h�A���� �E�\�@�@�h �ЊQ�\�h�͂̋����@�@�n��@�ւ̔\�͋��� �\��E�����x���@�@�@�@�ЊQ�����v��̐��� �E�y�@�@�� �R�n�ۑS���@�@�@�K�ȓy�؋Z�p�@�@�s�K�ȊJ���̐��� �y�n���p�Ǘ��ȂǂɊւ��鐭��E�v����胁�J�j�Y���̊J�� �Ď��A�x��V�X�e���̐��i �E���@�@�� �����̓w�͂ƎΖʍЊQ�y����@�Ƃ̓����@�@�I�n���ׂ�ЊQ�̖h�~ �ЊQ�����R�~���j�e�B�[�ƒn�搭�{�̎Q���ɂ��A�ΖʍЊQ�����ւ̓w�͂� (�S���I�A�Љ�I�A����ь��N�ʂ��܂�)�v��̎��{�B �����\�ȕ�����ۏႷ�钷���I�x���̒B ---2006�����s���v���蔲���@http://landslide.dpri.kyoto-u.ac.jp/2006-Tokyo-Action-Plan-J.pdf |
3�j����A���Ԃɑ��Ăǂ̂悤�ȋZ�p�̊J����]�݂܂����H
|
IPL�i���ێΖʍЊQ�����v��j�Ɉʒu�t�����邠����Z�p |
4�j���������̎葱���̕��@
|
���ɂ���܂��C���ł����}���܂��B ���݁C�ʎ��i��P��Ζʖh�А��E�t�H�[������Bulletin�j�̒ʂ�CIPL�𐄐i���Ă���̂ŁC���̒��ňꏏ�ɋ��������ł��邱�Ƃ��œK�ł��B |
4. �{�݂̗��p���@
�P�j�n���ׂ�Ɋւ���ǂ̂悤�Ȏ{�݂�����܂����H
|
�E�����n���ׂ�ϑ��� �E �e��n���ׂ�Č������@�i��1�`7���@�j �E ���̑��iRCL�p���t�Q�Ɓ@http://landslide.dpri.kyoto-u.ac.jp/pamphlet.htm�j |
�Q�j���p�p�x�͂ǂ̒��x�ł����H
|
�n�k�W�̌����҂̗��p�p�x�����܂��Ă����B |
�R�j�{�ݗ��p�̐\���ݕ��@�i���p�\�ł���j
|
RCL�܂ŘA�����������B |
5. �e�������ɂ���
�P�j���X���� ����
|
�g �D �E �� �F�ΖʍЊQ�����Z���^�[���i�h�Ќ������n�Ռ����O���[�v�����j �o�@�@�@ �� �F1993/2�C���s��w�h�Ќ��������� �� �� �� �� �F�n���ׂ�_�C�i�~�N�X�C���E�n���ׂ����͌��� �� �� �� �� �F�����������^���n���ׂ�̔����E�^���@�\�C�n�k���n���ׂ�̔����@�\�C�n���ׂ�Č������@�̊J���C������Y�n��̒n���ׂ�댯�x�]���̌����C��K�͒n���ׂ�̑O�����۔���ƒn���ׂ�ЊQ�\�� ��܁E�w�p�܁F�n���ׂ�w��_���܁C���ۗыƌ����@�֘A����c�܁C�y���[�������}�`���s�`�����_�� �w �O �� �� �F�i�Ёj���{�n���ׂ�w����CICL��CUNITWIN�����v��u�Љ�Ɗ��Ɏ����邽�߂̎ΖʍЊQ�댯�x�y���v�v���O�����R�[�f�B�l�[�^�[�C"Landslides"�ҏW�ψ��� |
�Q�j�����@�_ ������
|
�g �D �E �� �F�h�Ќ������n�Ռ����O���[�v �ΖʍЊQ�����Z���^�[�@�n���ׂ�_�C�i�~�N�X�����̈揕���� �o�@�@�@ �� �F1996/4�C���s��w�h�Ќ����������� �� �� �� �� �F�n���ׂ�_�C�i�~�N�X �� �� �� �� �F�n�k���n���ׂ�Č������@��p�����n�k���n���ׂ�̔����E�^�����J�j�Y���C�������������O����f�����@��p���������������^���n���ׂ�̔����E�^���@�\�CGPS��p�����n���ׂ�ړ��ϑ��@�ƎΖʌ��N�f�f�\�z�C�O��������f�ψʌv��p���������Њ�n���ׂ�̈ړ��ϑ��C�n���ׂ�̋�ԕ��z�E�K��-�p�x�W�̃t���N�^���\�� |
�R�j�����@�́@������
|
�g �D �E �� �F�h�Ќ������n�Ռ����O���[�v �ΖʍЊQ�����Z���^�[�@�n���ׂ�v�������̈揕�����i�����n���ׂ�ϑ����j �o�@�@�@ �� �F1987/12�C���s��w�h�Ќ����������� �� �� �� �� �F�n���ׂ�v�� �� �� �� �� �F�����Њ�n���ׂ�̒����ړ��v������ђn�����ϑ� |
�S�j���@����
|
�g �D �E �� �F�h�Ќ������n�Ռ����O���[�v �ΖʍЊQ�����Z���^�[�@�n���ׂ�_�C�i�~�N�X�����̈揕�� �o�@�@�@ �� �F2004/6�C���s��w�h�Ќ��������� �� �� �� �� �F�n���ׂ�_�C�i�~�N�X �� �� �� �� �F�j�Ӑ��n�Ղɂ�����n���ׂ�^���@�\�y�щ^���͈͗\���@�̌����C�Ζʕ\�w����h�~�ɂ�����A���J�[�̗L�����p�Ɋւ��錤���C���R�ɂ�����r�̏��J����n���ׂ�˔��ЊQ�̑O�����ۂ���щ^���\���C�����r���ʕϓ��ɂ��n���ׂ蔭���@�\�̉y�ї\����@�̊J�� |
�T�j���@���P
|
�g �D �E �� �F�h�Ќ������n�Ռ����O���[�v �ΖʍЊQ�����Z���^�[�@�n���ׂ�v�������̈揕�� �o�@�@�@ �� �F2003/11�C���s��w�h�Ќ��������� �� �� �� �� �F�n���ׂ�v�� �� �� �� �� �F�y���̗������̔����@�\�Ɋւ��錤���C����������̃��J�j�Y�� |
6. �Ō��
�P�j���Ԋ�ƂɊ��҂��邱�Ƃ͉��ł��傤��
|
���ɂ���܂��CICL�ɎQ�悳��C�����ɂƂǂ܂炸���ێЉ�ɂ��v���肢�����B |
�Q�j�Ζʖh�Б�Z�p����̃z�[���y�[�W���������Ƃ͂���܂���
|
����܂��B |
�R�j������̊��z��
|
�ǂ��ł��Ă���Ǝv���܂��B |
�S�j�Ζʖh�Б�Z�p����Ɋ��҂��邱�Ƃ͉��ł��傤��
|
���{�̍����Ζʖh�Б�Z�p�������݂̂ɂƂǂ߂��C�Ζʖh�Жʂ̃j�[�Y�̍����A�W�A�C���e���A�����J���̎Ζʖh�Ђɂ��v�����Ă������������B �܂��C�Ζʖh�ЂɊւ��鐢�E�I���͊����ɁC���ϋɓI�ɎQ��肢�����i�܂���ICL�ɉ���@�ւƂ��ĎQ�悳��邱�Ƃ�]�݂܂��j�B |
���肪�Ƃ��������܂����B
����ތ�L��
�@���X�����Ȃ�тɃZ���^�[�����̊F�l�ɂ́C���ɔM�S�ɃZ���^�[�̏Љ�����Ă��������܂����B�����́C���ɁC�L�����ێЉ�ւ̍v���Ɍ����āC�����ICL�ւ̎Q���M�]����Ă����܂��B��������C���㍑�����獑�ۂւ̃j�[�Y�����܂��Ă���Ǝv���܂��̂ŁC�{���������Č�������K�v������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B